『週刊Life is beautiful』6月17日号は、AIがコードを書く現場の話から恋愛アルゴリズム、切り抜き動画のビジネスモデルまで幅広い内容だったが、個人的に強く印象に残ったのは二つあった。一つはAIコーディング支援ツール「Claude Code」の実例、もう一つはAI普及が原子力投資にまで波及しているという話だ。
中島さんはMulmoCastというプロジェクトの開発でClaude Codeを実際に使っており、タイポ修正からTTS機能の追加まで、まるでジュニアエンジニアに指示するような感覚でAIに仕事を任せていた。コードレビューやリファクタリングは人間が担当し、AIには動くコードを書かせる。こうした役割分担によって、人間が一人でコードを書くより二~三倍の効率で開発できたという話はAIが現場で本当に力を発揮している証拠のように思えた。
そして将来的にはAIが人間のレビューを経ずにコードを書き、そのまま採用される時代が来るかもしれないという予測も語られていて、今の私たちがマシン語を直接書かずコンパイラに任せているのと同じ流れだと考えると、妙に腑に落ちるものがあった。
気になったのは、読者からの質問コーナーで触れられていた、AIの普及によるデータセンターの電力需要増加と、それに伴う原子力発電やウラン需要の再評価というテーマだ。
質問者が「今のうちに原子力やウラン関連株を買っておくべきか」と尋ねたのに対し、中島さんは「悪くない考えだと思います」と答えていた。この一言が妙に重かった。肯定的でありながらも具体的な銘柄やタイミングには踏み込まず、投資判断は自己調査に委ねている。そのニュアンスは、方向性としては正しいがリスクを理解した上で長期目線で考えるべきだという示唆に思えた。
確かにAIバブルと電力需給逼迫の組み合わせは、エネルギー投資の新しい切り口になる可能性がある。ただ同時に、規制や政策変更、ウラン価格のボラティリティ、原子力事故といったリスクも抱えている。海外ではCamecoやGlobal X Uranium ETF、日本では三菱重工や原燃関連企業が候補に挙げられるが、短期で利益を狙うよりメガトレンドとして腰を据えて注視すべきテーマだと感じた。
また、経理業務のAI化についてのやり取りも興味深かった。「淡々と実施できる作業はすべてAIに置き換わる」と言い切る一方で、システム連携や人事面など課題が多く、移行には10~20年かかるという冷静な見立てもあった。短期的には変化が遅く見えても、気づいたときには「AIなしでは戻れない時代」になっているという指摘は、経理に限らず多くの仕事に当てはまるだろう。
この号を読み終えて感じたのは、AIがコードを書き、そして電力やエネルギー市場にまで影響を及ぼすほど広がりつつあるという現実だった。エンジニアリングの世界も、経理の現場も、そして投資の世界までもがAIによって再編されつつある。原子力やウラン関連株への投資は「悪くない考え」という言葉の通り、長期的には注目しておくべきテーマだと思う。ただし、目先の値動きに惑わされるのではなく、メガトレンドを意識して腰を据えて向き合う必要がある──そんな気づきをもらえた号だった。
まとめ
・原子力、ウラン関連株は悪くない。
・淡々と実施できる作業はすべてAIに置き換わる。
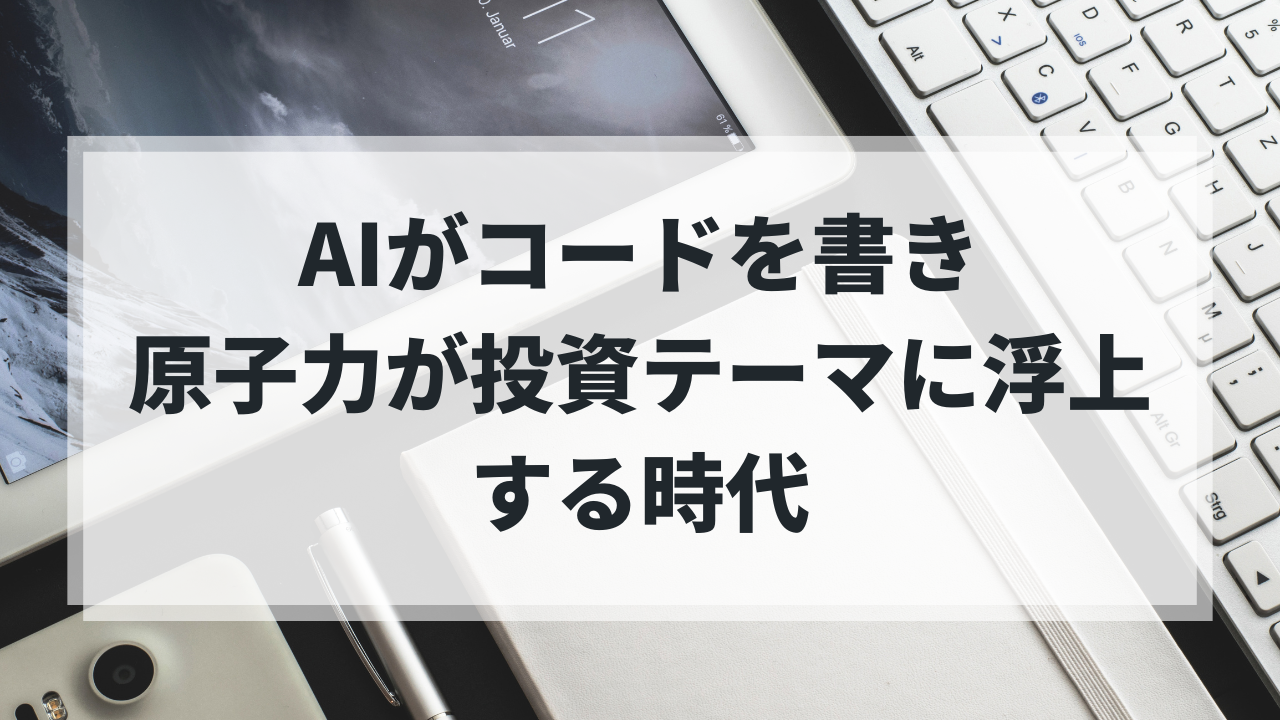
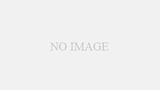
コメント